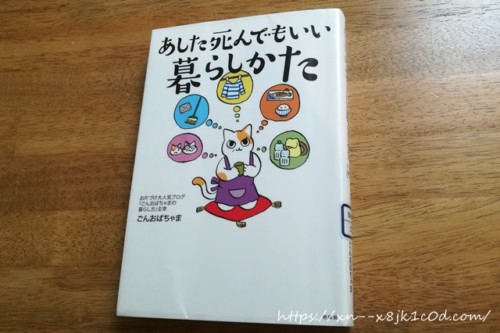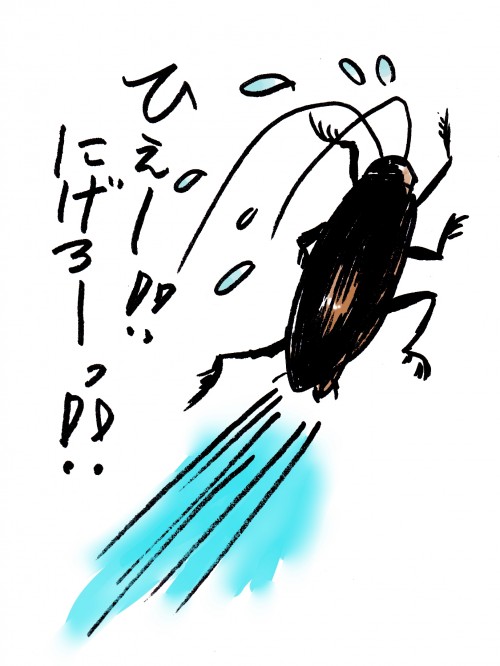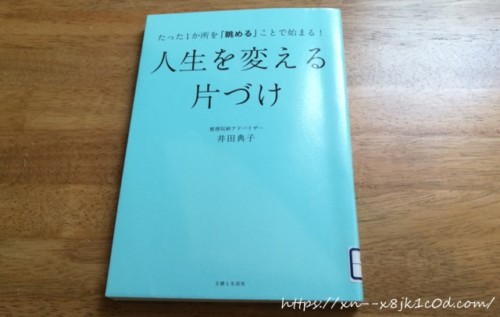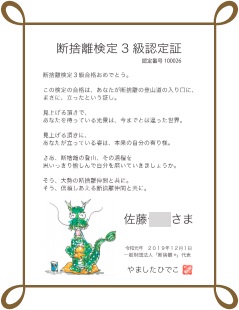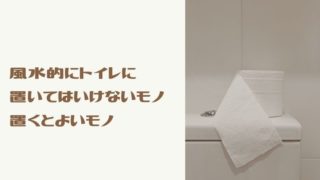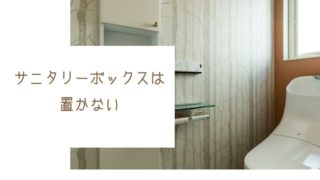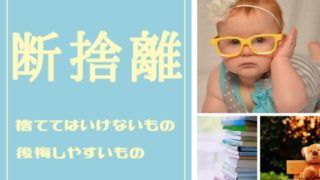人間はいつ死んでしまうか分かりません。
願わくば、いつ死んでも後悔しないように生きたい!ですよね。
そこで、お片づけブロガーごんおばちゃまの本「あした死んでもいい暮らしかた」というタイトルが気になり読んでみました。
さて。
どんなことをしたら、いつ死んでもいいと思えるような人生になるんでしょう?
本書は257ページありますがせめてこれだけはやっておかないと後悔しそう!すぐやらなくちゃ!と思ったことをまとめました。
ぜひチェックしてみてください。
- 使えるモノを捨てることが苦痛
- 断捨離しているけど、物が減らない、減らせない
- 生前整理したいけど、どうしたらいいか分からない
- ぽっくり死んでも家族が困らないようにしておきたい
- 後悔のなく、一生を終えたい
あした死んでもいい暮らしかた(ごんおばちゃま)の片付け本感想まとめ
本を読んでまず思ったことは「あした死んでもいい暮らしかた」というのは、私にとっては「人生にケリ」をつけていく暮らしかた。
つまり生前整理をしていくことだな、と感じました。
いつ死んでも、後悔しないためには
- 毎日楽しんで暮らしたい
- 好きなモノを食べたい
- やったことがないことに挑戦してみたい
など、
どんな暮らしをしたいか、ということを考えることも大事。
だけど、私は、自分がいつ死んでも、家族が困らないようにしておきたいと真っ先に思ったのです。
そのために、本書を読んですぐにやらなくちゃ!と思ったことは、次のようなことです。
モノは減らして暮らす
使っていないモノが押入れを占領し、本来使っているモノがしまえずに放り出されているなんて、もったいない話ですし、残念なことです。
引用元:48ページ
わたしは、
- これは、いつか使うかもしれないモノだから
- これは、高かったから
- これは、思い出深いものだから
- これを捨てるとバチが当たりそうだから
といって、押入れの奥にしまいこんで、何年も眠らせているものがあります。
圧力鍋
本
◆ 高くて捨てられないモノ
振袖
◆ 思い出深いモノだから捨てられないモノ
卒業アルバム
写真
子供が書いた絵
◆バチが当たりそうで、捨てられないモノ
お人形
大切に片付けてあるからといって、目を通すことも、手入れすることもなく。
現時点で、死蔵品になっています。
これらは、捨ててしまうと二度と手に入らないものなので、そういった点では確かに大切なものではあるけれど、使っていないモノに違いありません。
使っていないモノが押入れを占領していて、今使っているモノを片付ける場所がなく放り出されている状態というのは、確かにおかしいですよね・・・。
だからといって、今すぐに捨てる気にはなれませんが、自分の気持ちと向き合い検証する必要はありそうです。
使わないものは家に入れない
私はホテルに用意してあるモノも持ち帰りません。家にはちゃんと自分が好きな石鹸や、歯ブラシがスタンバイしています。お気に入りを使いたいので持って帰ってもきっと使いません。
得とか、損とかではなく「使うか使わないか」でそうしています。
引用元:84ページ
ホテルにある歯ブラシやヘアブラシ、シャンプーキャップ、かみそりなど持ち帰りOKなアメニティグッズは、料金に含まれていますよね。
なので、私は持ち帰っていました。

ウェルカムドリンクとして準備されているティーバックやインスタントコーヒーなどもです。
それは、持ち帰らないと「損」した気分になるから。
使えば、「損」したことにはなりませんしね。
ですが、こういった持ち帰ったもの全てを消費しているかというと、そうではないんですよね。
使わないモノは「ゴミ」として処分してたりします。
なら、はじめから持ち帰らないほうが、いいですよね(*´∇`*)
余分なモノは置かない
未来でもなく過去でもなく今、今が大事です。
過去に心を残さず、未来にばかり目を向けず、今を生きる。
引用元:86ページ
家にある物を見回すと、今現在使っているモノは、ほんのわずかです。
何があるかというと
過去に使っていたけれど、今は使っていないモノ。
未来に使うかもしれないけど、今は使っていないモノ。
こういったモノが大半を占めています。
今、使っているモノだけを残して、他のものを全て捨ててしまったら、8割のモノが捨てれるんじゃないかな?と思ってしまうほど、今使っているモノは少ないです。
割り切って捨てることができたら、どんなにスッキリするでしょう☆
でも、それができない・・・ので。
未来に使うかもしれないと思うモノに関しては、いつまでに使うのか。
期限を設けることにしました!
その期限までに使わなかったら、即断捨離する。
過去に使っていたけれど、今は使っていないモノは、すぐに捨てる。
そして、すぐに使わないモノは、購入しない。
とすれば、物は減ってしくはずです。
片付けは1日30分やる
私の片付けは毎日30分だけです。
しかも不要なモノを抜くだけです。
30分のタイマーが鳴ったらやめます。
整理整頓はしません。
モノが減って大事なモノだけになった時初めて取りかかります。
整理整頓や後片付けをしないので毎回楽しく楽にできます。
引用元:92ページ
「後から片付ければいいや。」と思っていると、「後で。後で。」と先送りして、どんどんモノが溜まってしまうのです~。
モノが溜まってしまうと、片付けるのがさらに億劫になって、「後で。時間がある時にやろう。」と思います。
でも、時間がある時って、なかなかないんですよね。
なのでわたしも、15分片付けることからはじめています。
15分というのは、筆子さん方式です。
わたしにとって30分は長いので、15分だけ片付ける。
もし15分で片付け切れたら15分で終了。
片付け切れなかったら、休憩したり別の用事を済ませた後、改めて15分片付けるというかんじです。
抜くモノは「使う」「使わない」で決める
「いる」「いらない」の基準は人によって様々です。どのように考えても答えは永遠に見つからない・・・。みんなが一致する正解はないのです。
それではこの基準を「いるか、いらないか」ではなく「使うか、使わないか」で考えていくと、もっと物事ははっきりしてくるはずです。
引用元: 95ページ
断捨離的な考えでは「必要か」「不要か」見極めていきます。
が、確かに「必要(いる)、不要(いらない)」という判断は難しいのです。
例えば粗品で、お皿をもらったとします。
粗品といえども、新しいお皿だったら、欠けたり割れたりしていないので、使えますよね。
使えるモノを捨てるのはもったいない、だからいるもの、とジャッジしてしまいがちです。
でも、実際に使いたいと思うのモノじゃなければ、それは使わないので、いくら使えるモノであっても、それはいらないモノなんですよね。
だからごんおばちゃまが推奨されている「使うか、使わないか」で考えたほうが、分かりやすく、ジャッジしやすいと思いました!
私にとって「抜く」というのは「間引きする」というイメージ。
捨てる、というとなんだか悪いことをしているようで気がひけてしまうんですが「抜く」と考えると、やっている行為は「捨てる」という行動であっても、なぜか精神的に楽なので「抜く」という言葉を採用しています。
自分のモノは自分で処分する
可愛い子供たちに、自分たちがいなくなった後で苦労をかけないようにしたいものです。
私たちは「自分のことは自分でするのよ」と子供を育ててきました。
親の教えを守ってきた子供たちに私たちの面倒をかけるのは、その教えに反しています(笑)。
引用元: 99ページ
もしわたしがぽっくりと死んでしまったら・・・
わたしのモノの処分に、子供たちが四苦八苦することになります。
子供たちにとっては、自分のものじゃないので、思い入れがなく捨てやすいモノばかりかもしれません。
でも、自分のモノの始末を子供に押し付けるのは、気がひけます。
立つ鳥後を濁さず。
鳥でさえ、ちゃんと後片付けをしてから飛び去っていくのです。
捨てられない・・・なんて言ってられないな~と思いました。
掃除は決まった時間にする
毎日掃除をしていると、掃除しない日は落ち着きません。
しかもやるのはいつでもいいのではなく、朝8時と決めたなら8時になれば必ず雑巾と掃除道具をもって掃除をするようにする。
時間を決めて掃除することで習慣として身につきます。
引用元:128ページ
この文章を読んで、はたと毎日掃除していないことに気が付きました。
義務教育の間は、否が追うにも掃除の時間というのがあって、掃除していたはずなのに・・・。
汚れていることに気が付いたら掃除するのではなく、決まった時間にお掃除すればいいですね( ̄. ̄;)
すべてのモノを把握する
我が家では、どこに何があるか、家族にもすべてわかるようにしています。
モノが少ないせいで片付けも楽です。洗剤やトイレットペーパーなどのストックもないので、収納棚はガラガラです。
引用元:151ページ
使いたいと思った時に、ないと困るモノ。
ストックして当たり前だと思っていました。
例えば・・・
洗剤、石鹸
トイレットペーパー、ティッシュペーパー
マヨネーズやケチャップなどの調味料。
カレーのルーや缶詰。
ラップ、アルミホイル
コンタクト用品
生理用品
洗剤、シャンプー、リンス、トリートメント
食器用のスポンジ、お風呂用のスポンジ
腐るものじゃないから、安いときに買ったりとか・・・。
でも、あるのに買っちゃったりするんですよね。
確かに、ストック品がなければ、収納庫はガラガラでしょうし、二度買いすることもない気がします。
ないと不安。
だけど、今どき夜遅くまでスーパーもやってるし、コンビニは24時間営業しています。
特売品で買うより高いお値段で買うことになるけれど、なくてもさほど困ることはないかな~と思いました。
それより「スッキリ」を実感してみたいので、ストック品ゼロを目指します(*´∇`*)
家計簿をつける
一年間のチェック
○水道代(上水、下水)
○電気代
○ガス代固定費のチェック
○自動車税
○固定資産税
○保険代
○ケーブル代
○固定電話見直し対象
○保険代
○塾代、習い事の月謝
○携帯電話本当にこれだけいるのだろうか?と疑ってみます。
必要と思っているモノが、本当は必要ないかもしれません。引用元: 193~194ページ
今まで何度トライしようと思っても、長続きしなかったんです。
「家計簿」
毎月やるのは大変だけど、上記の項目だけなら、通帳をチェックすればできることなので、やってみようと思いました!
片付けの終末が来た
毎日わずかな時間でやってきた「抜く」作業を積み重ねた結果、最後には生前整理まで終わってしまいました。
夫婦2人、今、少しの荷物で日々の暮らしができて、毎日楽しく過ごしています。
引用元:246ページ
今家にある物を片付けることは、気が遠くなるような作業です。
でも、わずかな時間でいい。
わずかな時間「抜く」だけで、生前整理まで終わってしまう!と考えたら、ワクワクします~。
スッキリとした暮らしができる!
身も心も軽くなる!
そんな感じです。
さ~、これから何を抜こうかな。
まとめ
今日は人気ブロガーごんおばちゃまの本「明日死んでも いい暮らしかた」を読んで、これだけはやらなくちゃ!と思ったことを紹介しました。
正直のところ、今の私は、やっていないことが多いので、明日死んでもいいとは、言い切れません。
でも、近いうちに。
明日死んでもいいといえるように。
着々と生前整理をしていきたいという気持ちが強くなりました(*´∇`*)
そのためには、何はともあれ、今使っていないモノを「抜く」こと!!!
頑張りまーす。